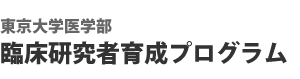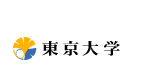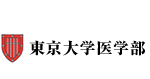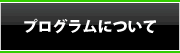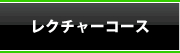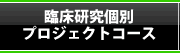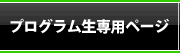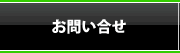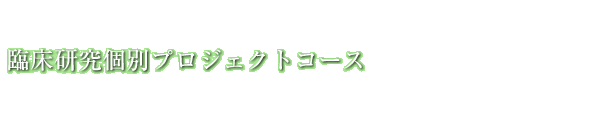臨床研究個別プロジェクトコース紹介
Mental Health Research Course 2020年度のプロジェクト
2020年度のMental Health Research Courseは、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の影響を考慮し、オンラインで開催いたします。精神神経科のスタッフを中心に指導層からのミニレクチャーをオンラインで提供すると共に、メンタルヘルスとその研究に関わる多角的な議論を参加者と一緒に深めて参ります。
Mental Health Research Courseについて
本コースは基礎から臨床まで幅広くmental health に関係する教室(こころの発達医学、疾患生命工学センター構造生理学部門、神経細胞生物学、神経生化学、神経生理学心療内科学、精神医学、精神保健学、分子精神医学講座、ユースメンタルヘルス講座、リハビリテーション部)が集まって作られたものであり、それぞれの分野より教育に熱心な人材が集まり、メンタルヘルスに関するあらゆる臨床・研究について幅広く知識を得て、学ぶ機会を持つようにしています。
2010年初年度に関しては、まず初回に参加者の皆さんの興味やニーズをお聞きし、全員にmentorをつけて、継続的にfollow upする体制を整えました。また、学生さんの興味が他にもあった場合はmentor同士が連絡を取り合って柔軟に学生さんの希望にそえるようにしました。2011年度、2012年度に関しても同様に参加者の皆さんのニーズをお聞きして、継続して参加される方にも満足いただけるようにプログラムをアレンジしました。
情報提供の方法としては、第一に、全員のメールアドレスをメーリングリストに登録させていただいて、様々な教育的な講演などの案内を頻回に流すようにしております。第二に、mentorを通じて、研究室への出入りなども自由にできるように配慮し個別の勉強会に参加できるように配慮いたしました。
定例ミーティングは、2010年度は、毎月1回土曜日の15時から全体のmeeting を行い、参加教室の紹介、教育的講演、Journal Clubを行いました。講演に関しては、学生さんの希望を聞いて、指導医がアレンジを行い、さらに講演内容も学生さんの要望を取り入れました。毎月学生や教官も含め10名くらいが集まりアットホームな雰囲気で開催しております。教育的講演の内容によっては、多くの方々に参加いただくこともありました。2011年度には14時からNIHのvideo sessionを熱意ある教官と有志が集まって、勉強しながら聞く試みも行いました。2012年度からは、より参加しやすいよう日時を金曜日18時と変更いたしました。後半にはLab tourも行い、教官も楽しみながら、研究室を訪問する機会を持ちました。2014年度は精神科臨床研究ミーティングと同時開催とし、実際に臨床の第一線で働きつつ、研究をすすめている教官や院生が参加しました。2015年度は精神科若手スタッフが中心となって、後期研修医も参加し、より充実した教育的コースに改変いたしました。
2016年度からは毎月1回金曜日19時からの勉強会に加えて、指導医、大学院生、後期研修医、初期研修医、医学生によって構成される研究チームに所属し、それぞれのチームミーティングに参加し、研究に取り組むことが可能となっております。本コースから、医学生や研修医を筆頭として学会発表や論文執筆へとつなげることができるようになっています。また、希望者には、指導医に同行して、精神科医療や地域精神保健の現場を見学実習する機会も提供しています。
毎月の勉強会の場所は東大病院クリニカルリサーチセンターA棟1階・精神科医局となっております。ふるってご参加ください。
参加教室・参加教員の構成
| 参加教室 | 参加教員 |
|---|---|
| 精神医学 | 笠井清登、神出誠一郎、荒木剛、安藤俊太郎、近藤伸介、市橋香代、 里村嘉弘、岡田直大、多田真理子、池亀天平、森田健太郎、 金原明子、 熊倉陽介、森田正哉、川上慎太郎、木内拓、清野知樹、森田進 |
| 心療内科学 | 吉内一浩 |
| 精神保健学 | 川上憲人 |
| こころの発達医学 | 金生由紀子 |
| 神経生理学 | 狩野方伸、菅谷佑樹 |
| 神経細胞生物学 | 岡部繁男 |
| 神経生化学 | 尾藤晴彦 |
| 疾患生命工学センター 構造生理学部門 |
河西春郎、柳下祥 |
| 臨床疫学・経済学 | 康永秀生、山名隼人 |
本コースの目的
「No health without mental health」(Lancet, 2007)との標語に代表されるように、からだの健康とともにこころの健康を育み、守ることは、国民一人一人の大切な権利であり、国家全体の幸福度を高めるために必須である(Nature, 2008)。精神疾患による社会的損失は甚大であり、その克服は国家的課題である(Nature, 2010)。一方、身体疾患をもつ患者は精神保健的問題を合併する頻度が高く、身体疾患をもつ患者のQOL向上とその疾患自体の予後のためにも精神医学・心身医学的支援が有用である。近年の医療は、evidence-based medicineを土台にしながらも、patient-centered approach, value-based medicineへと止揚しつつある。このような全人的医療の達成には、こころの健康に関する医学教育が欠かせない。
こころの健康に、生物学的、心理学的、社会医学的などの多面的な観点から関わる優れた臨床研究者を育成するために、学際的な多分野の教員からなるコンソーシアムを形成し、医学生や研修医と共に未来型のメンタルヘルス、ひいては未来型の医療についての洞察を深めていきたい。このような臨床・研究を学びたい、こんな活動をしてみたい、といった学生さん一人一人のニーズにきめ細かく応え、学生さんとともに本コンソーシアムを育てていきたいと考えている。
2020年度の活動予定
| 6月19日(金) | オリエンテーション、自己紹介 |
|---|---|
| 7月3日(金) | 分子精神医学入門(神出) |
| 8月15日(土) | サマーセミナー |
| 8月29日(土)・30日(日) | 新学術領域若手合宿・領域会議(Zoom) |
| 9月26日(土) | リトリート(Zoom) |
| 10月23日(金) | 脳画像研究入門(岡田) |
| 11月20日(金) | 国際思春期保健と東京ティーンコホート(安藤) |
| 11月29日(日) | TICPOCシンポジウム |
| 12月18日(金) | 総合病院精神医学(近藤・井上) |
| 1月8日(金) | 臨床と研究の民主化(金原) |
| 2月26日(金) | 臨床疫学入門(山名) |
| 3月19日(金) | 震災支援(荒木) |
2019年度のプロジェクト
Mental Health Research Courseに参加する医学生もしくは研修医は、以下のプロジェクトの中から一つを選択し、各プロジェクトチームのメンバーの指導を継続的に受ける。希望する場合には、研究ミーティングや様々な研究・臨床の現場の取り組みに同席し、体験型の実習を行う。
【プロジェクト一覧】
| Aプロジェクト | 病態解明につながる分子精神医学研究を学ぶ |
|---|---|
| Bプロジェクト | 回路精神医学(MRI/EEG/NIRS/early psychosis) -こころの脳神経基盤の解明とバイオマーカーの開発- |
| Cプロジェクト | 疫学研究の理解と体験 -東京ティーンコホートデータを用いて- |
| Dプロジェクト | 臨床疫学研究の実践 -精神科病棟に入院した未成年患者の後方視ケースシリーズ- |
| Eプロジェクト | Co-production of research 統合失調症研究の当事者・家族との共同による優先順位づけ |
【各プロジェクトの紹介】
Aプロジェクト:病態解明につながる分子精神医学研究を学ぶ
| 指導メンバー | 神出誠一郎、池亀天平、木内拓、浅井竜朗(協力メンバー:柳下祥、田宗秀隆、水谷俊介) |
|---|---|
| 内容 | DNAマイクロアレイや次世代シークエンサーといったゲノム解析技術の進歩に伴いヒトの遺伝子研究やエピジェネティクス研究も盛んに行われ、またヒトでの知見に基づいた細胞やモデル動物を用いた分子生物学的研究とともに、困難と思われた精神疾患の病態解明に迫ろうとしている。当チームでは当科だけでなく、最先端の分子精神医学研究を進めている当科と関連の深い研究者の協力のもと、以下の内容を予定している。 ・当科や当科と関連の深い基礎神経科学研究者の研究室と共同で開催する精神疾患関連の基礎的研究に関する勉強会・抄読会に参加し、現在注目されている仮説や最新の研究手法とこれにつながる考え方について学ぶ。 ・当科に加え、上記の基礎神経科学研究者の研究室紹介に参加し、研究テーマや背景となる仮説、必要な手法や設備等について研究者本人から直接学ぶ。 ・参加される方とのご相談の上で、実際の実験手順を体験していただき、それぞれの手順の意義を知り、また希望に応じて発展させることも可能である。 |
Bプロジェクト:回路精神医学(MRI/EEG/NIRS/early psychosis) −こころの脳神経基盤の解明とバイオマーカーの開発−
| 指導メンバー | 岡田直大・荒木剛・多田真理子・森田進・川上慎太郎・臼井香 |
|---|---|
| 内容 | MRI/EEG/NIRSは、生体内の脳構造や脳機能などの定量評価が可能で、有用性が高い。ほぼ非侵襲的な検査で、被験者の負担が少ないことも長所である。精神疾患や心理行動学的特徴の、脳神経回路基盤の解明やバイオマーカーの開発を目指し、MRI/EEG/NIRSを用いた研究成果が各国から多数報告されている。精神疾患を対象とした脳神経回路研究は、病態に関連する客観的な所見を明らかにすることで、患者本人や家族などの病態に対する理解を深め、社会全体の精神疾患に対する偏見を減らすことにも、大きく貢献すると考えられている。 私たちは、早期精神病を中心とした精神疾患をもつAYA(Adolescent and Young Adult)世代を対象としたMRI/EEG/NIRS研究により、精神疾患の発症と、予防や回復(リカバリー)に寄与する回路基盤の理解を目指している。並行する思春期コホートでのMRI/EEG研究では、心理行動学的な発達の脳回路基盤に注目している。これらの取り組みの統合としてAYA世代の心理支援法の開発を始めており、ヒトの主体価値の発展に重要なAYA世代の患者が、個人の価値観や希望に沿う回復(パーソナルリカバリー)を目指せる動機付けの工夫を検討している。支援法開発は、研究者、臨床家、当事者など多様なメンバーで行う共同創造(コプロダクション)とする予定である。 本チームでは回路精神医学研究に関して、指導メンバーによるサポートのもと、参加者の希望に応じて、下記の機会を得ることが可能である。 ① 論文の抄読会に参加し、回路精神医学に関する最新の知見からの学びを通じて、研究に必要な基礎的な知識や解析手法を習得し、論理的思考力を高める。また参加者自身が発表する機会においては、その準備の過程を通じて、プレゼンテーションの技術を身につける。 ② リカバリーへの支援法開発のための抄読会やインタビュー調査の流れに立ち会う。 ③ 当科で進めているMRI/EEG/NIRS研究の、データ取得の実際を体験する。MRIについては、2019年に本学ニューロインテリジェンス国際研究機構(IRCN)に導入された、最新型のMRIマシン(Siemens Prisma機)による撮像に立ち会う。 ④ 当科で進めている、早期精神病等の精神疾患を対象としたMRI/EEG/NIRS研究や、思春期健常者を対象としたコホート研究「東京ティーンコホート」のMRI/EEG研究に実際のデータを用いた解析を経験することにより、脳回路データ解析の基礎を学ぶ。 なお参加者の希望や研究の進捗状況に応じて、学会発表や論文化の支援も検討可能である。 |
Cプロジェクト:疫学研究の理解と体験 −東京ティーンコホートデータを用いて−
| 指導メンバー | 安藤俊太郎、森田正哉、清野知樹 |
|---|---|
| 内容 | 思春期は、こころと身体が劇的に成長する重要な時期である。不安症、統合失調症の発症時期と重なることから臨床的にも関わりの深い期間ではあるが、精神疾患のみならず学校生活、家族関係、自己への葛藤などさまざまな影響がみられることでも知られている。一方で思春期を対象とした大規模な疫学調査は本邦では殆ど実施されておらず、思春期児童がどのような要因に影響されているかなど、明らかな関連は多くない。本チームが主体となって実施している東京ティーンコホートは、本邦初となる大規模思春期コホート調査であり、これまで5年に渡りデータを収集している。疫学データを解析することで児童の発達と生活習慣、家族要因、友人との繋がりなどの関連性を明らかにすることが可能となり、思春期におけるこころの健康に寄与することを最大の目的としている。 本チームでは、東京ティーンコホートの疫学データを用い、実際に統計解析を行う体験や、他国の調査との比較などを行うことで、疫学研究に対する理解と統計解析の基礎を学ぶことができる。昨年度は10歳時の子供たちの自由記述回答と2年後の精神症状との関連を調べた研究を実際に行い、その過程を通じて先行研究の調べ方、仮説の立て方、研究計画の立案、解析の実施、結果に対しての考察と発表を実施することができた。今年度は、昨年度の解析結果を踏まえつつ、自由記述回答を用いてさらに発展させた縦断研究を行う。また、昨年度得られた重要な知見に基づく論文化指導と、希望者に応じ、学会発表を行う方針である。 |
Dプロジェクト:臨床疫学研究の実践-精神科病棟に入院した未成年患者の後方視ケースシリーズ-
| 指導メンバー | 近藤伸介、市橋香代、里村嘉弘、山名隼人、熊倉陽介 |
|---|---|
| 内容 | 日々の臨床実践を振り返り、診療の改善につながる報告をすることは、臨床研究の第一歩である。本チームでは、臨床データを収集し、臨床研究として報告するまでのプロセスを学ぶことができる。精神疾患は思春期に発症しやすいことが知られている。小児期から思春期におけるメンタルヘルスの不調に対して適切な支援を提供することは、その後の生活や人生において非常に重要である。東京大学医学部附 属病院では、精神神経科とこころの発達診療部(児童精神科)の密接な連携のもと、小児期から成人期までの幅広い年齢層の精神疾患に対する診療を行っている。本プロジェクトでは東京大学医学部附属病院の診療録を参照し、過去2年間に当科に入院となった未成年の患者について調査し、精神医学的診断、生活史、発達状況、家族背景、治療経過などについてケースシリーズとして報告する。現場の指導医と精神保健・臨床疫学の研究者が協働するサポート体制のもと、 参加者の希望に応じて、下記の機会を提供する。 ①平成32年度の精神科関連学会(総合病院精神医学会、精神科救急学会、社会精神医学会、精神神経学会、統合失調症学会など)で、上記の内容に関して発表する。 ②同テーマに関して論 文の執筆と投稿を行う。 ③更に意欲的な者であれば、同テーマや類似のテーマに関して、全国規模のデータベース(DPCデータベースなど)に適用した大規模臨床疫学研究を行う。 ④地域における子ども家庭支援や虐待対策の現場やそれに関わる研究班へのオブザーバー参加を指導医の引率のもとで行う。また、子ども食堂や学習支援など、未成年を対象とした支援の現場への見学参加を指導医と共に行う。 |
Eプロジェクト:Co-production of research 統合失調症研究の当事者・家族との共同による優先順位づけ
| 指導メンバー | 金原明子、森田健太郎、笠井清登 |
|---|---|
| 内容 | 「統合失調症について研究すべき重要事項を当事者とともに考えランキングする調査研究」を日本で行うことを目標に、文献レビューや準備を行います。 臨床研究では、研究テーマや方法を考える際にFINER(Feasible, Interesting, Novel, Ethical, Relevant.)という5つの基準を満たしているかを検討します。中でも「研究テーマが患者さんにとって切実な問題か」が、研究立案において最重要視されるべき事項であると言われています。(Hulley 2013) 2004年UKで設立されたJames Lind Allianceでは、様々な疾患について、当事者・医療者などが「治療に関する未解明なこと:研究してほしいこと」の順位づけをしています。統合失調症治療に関しては、当事者・医療者などが参加し、質問紙調査・ワークショップ・既存の研究成果の文献レビューなどを経て、「統合失調症研究の10の優先事項」を決めました。(Lloyd 2011 Nature) 優先事項の検討だけでなく、研究の立案から普及・現場での実施における当事者参画も重視されています。Nature Editorials 2018では、「研究成果は誰かに見つけてもらい使ってもらえる日を待つばかりで、あまりにも多くの研究が、人々に還元されていないが、企画段階から当事者と専門職が共同で考えて創り上げていく共同創造(co-production)は、より良い社会・より良い研究につながっていく。」と指摘しました。研究成果の待ちぼうけ現象に対して「研究成果の普及・実施」に関する科学(Dissemination & Implementation science)が課題解決に取り組んでおり、その一つとして、診療の質評価指標(Quality Indicator)を取り入れること、当事者と共に評価指標を創り、当事者と共に医療や組織を評価することが挙げられています。 今年度のMHRCは、当事者や精神疾患の経験をもつピアサポートワーカーとのCo-productionによる「研究優先順位づけ」「研究究成果を拡げ現場で実施することの科学」「診療の質評価指標」に関する情報収集・文献検索を行います。 |
2019年度の活動予定
| 5月10日(金) | オリエンテーション |
|---|---|
| 6月7日(金) | A,B |
| 7月5日(金) | C,D |
| 8月2日(金)・3日(土) | 精神神経科サマーセミナー(MHRC参加推奨) |
| 9月13日(金) | E |
| 10月5日(土)・6日(日) | 精神神経科リトリート(MHRC参加推奨) |
| 11月1日(金) | A |
| 12月6日(金) | B |
| 1月10日(金) | C |
| 2月21日(金) | D |
| 3月13日(金) | E |
実際の活動(2018年)
|
5月18日(金) |
オリエンテーション |
|---|---|
| 6月29日(金) | ミニレクチャー 「研究の最初の一歩」 講師:金原明子先生 東京大学附属病院精神神経科 ミニレクチャー 「論文を探す・読む・まとめる」 講師:山名隼人先生 東京大学大学院医学系研究科 ヘルスサービスリサーチ講座 特任助教 各プロジェクトから計画の発表 |
| 7月13日(金)、14日(土) | 精神科サマーセミナー(MHRC参加推奨) |
| 9月21日(金) | 講演 「行動変容をうながすヘルスコミュニケーション」 講師:奥原剛先生 東京大学大学院医学系研究科医療コミュニケーション学分野助教 ミニレクチャー 「学校における自殺対策の現状」 講師:金田渉先生 帝京大学医学部精神神経科学講座助教 グループワーク 「学校に掲示する『自殺対策啓発ポスター』の制作 」 |
| 10月19日(金) | 各プロジェクトからの進捗報告 |
| 11月16日(金) | 講演 「北海道浦河町ひがし町診療所の取組」 講師:ひがし町診療所 川村敏明先生(院長)、高田大志先生(PSW)、泉祐志先生(PSW)、木村貴大先生(PSW)、塚田千鶴子 先生 (Ns) |
| 1月25日(金) | 講演 「公衆衛生大学院留学とグローバルメンタルヘルス、精神科医療の役割について」 講師:大熊彩子先生 東京大学医学部附属病院精神神経科 |
| 2月22日(金) | 臨床疫学チームからの進捗報告 「救急車で来院した自殺未遂者の後方視ケースシリーズ」 発表者:松原丈二、増田康隆、青木智乃紳、小畑聡美、熊倉陽介、山名隼人、市橋香代、近藤伸介 ミニレクチャー 「自殺について」 講師:近藤伸介先生 東京大学医学部附属病院精神神経科 ミニレクチャー 「死にたいと向き合う」 講師:熊倉陽介先生 東京大学大学院医学系研究科精神保健学分野 |
| 3月15日(金) | 進捗報告 「ピアサポートについて」 発表者:藤原実咲さん 思春期コホートチームからの進捗報告 「利他的な行動を賞賛されることが思春期児童に及ぼす影響」 発表者:田中正純、西村久明、長岡大樹、倉持菜々美、清野知樹、森田正哉、安藤俊太郎 |
実際の活動(2017年度)
| 5/12(金) | オリエンテーションとプロジェクト紹介 |
|---|---|
| 6/16(金) | ミニレクチャー「研究の最初の一歩」 講師:金原明子先生 |
| 7/29(土) | 精神科サマーセミナー(MHRC参加奨励) |
| 9/8(金) | 初期研修医発表「VBMの手法を用いた統合失調症の画像解析について」 発表者:熊谷友梨香先生(初期研修医) ミニレクチャー「MRI研究について」 講師:岡田直大先生 |
| 10/27(金) | 初期研修医発表「日本、英国に学ぶ長期疫学研究の展望」 発表者:永野渓舟先生(初期研修医) 学生発表「思春期におけるうつ徴候の遺伝的影響」 発表者:相澤隆寛さん(M2) ミニレクチャー「東京ティーンコホート研究について」 講師:安藤俊太郎先生 |
| 11/25(金) | BESETO(MHRC参加奨励) |
| 12/8(金) | 講演「みて聴いて感じる地域連携~より良い当事者支援のために~」 講師:清野知樹先生(吉祥寺病院) |
| 1/12(金) | 学生・初期研修医発表「ステロイド誘発性精神障害 ~当院リエゾンコンサルト患者における症例検討~」 発表者:高橋優輔さん(M2)、八木優子さん(M2)、緒方優先生(初期臨床研修医) |
| 2/23(金) | 講演「価値のシナプス神経基盤と精神医学研究の今後について」 講師:柳下祥先生(東京大学大学院医学系研究科 疾患生命工学センター 構造生理学部門 助教) |
| 3/16(金) | 学生発表「統合失調症におけるミスマッチ陰性電位振幅の減衰」 発表者:長谷川友宏さん(M2) レクチャー「論文を探す・読む・まとめる」 講師:山名隼人先生(東京大学大学院医学系研究科公共健康医学専攻 臨床疫学・経済学) |
実際の活動(2016年度)
| 6月17日(金) 19時〜 |
「研究ことはじめ」 清水夕貴さん(M4)・金原明子 |
|---|---|
| 7月8日(金) 19時〜 |
「うつからのリカバリー〜リカバリーセンター始動からの学び〜」 相澤隆寛さん(M1)・川上 慎太郎 「精神分析的人格理論の基礎」 秋山果穂さん(M3)・榊原英輔 |
| 9月16日(金) 19時〜 |
「医学生・研修医向け『臨床』研究入門 〜大規模データベースを用いた臨床疫学研究の紹介〜」 山名隼人先生(臨床疫学教室) |
| 10月21日(金) 19時〜 |
「気分障害・統合失調症のエピジェネティクス」 緒方優先生(初期研修医) |
| 11月18日(金) 19時〜 |
脳画像コラボ企画「MRIとNIRS―臨床応用に向けた脳イメージング研究」 「構造MRI・NIRSを用いた機械学習による大うつ病・双極性障害の診断について」 福沢紘揮さん(M3) 「思春期における環境及び性格傾向と脳構造の相関への準備(Tokyo teen cohort)」 森俊輔先生(初期研修医) 「NIRSを用いたうつ病の異種性の検討にむけて」 庄司昴先生(初期研修医) 「MRIの研究について(MRI/NIRSの相補的利用も含む)」 岡田直大 「近赤外線スペクトロスコピー(NIRS)の基礎と応用」 榊原英輔 |
| 1月20日(金) 19時〜 |
「精神科医療現場における暴力を考える」 出渕弦一先生(後期研修医) 「発達障害検査入院についての質的な調査について」 大熊彩子先生(初期研修医) |
| 2月17日(金) 19時〜 |
「サイコオンコロジー 〜がん患者の精神的ケア〜」 平山貴敏先生(国立がん研究センター中央病院精神腫瘍科) 「がん患者を対象とした精神療法」 清水研先生(国立がん研究センター中央病院精神腫瘍科) 「サイコオンコロジー事始め」 内富庸介先生(国立がん研究センター中央病院精神腫瘍科) |
| 3月3日(金) 19時〜 |
MHRC今年度の振り返り |
実際の活動(2015年度)
場所:全て精神科医局
| 4月24日(金) 18時~ |
1st meeting オリエンテーション |
|---|---|
| 5月29日(金) 18時~ |
2nd meeting 「医療と司法と福祉のはざま」 司会 熊倉陽介先生 ○司法精神医学に関する疑問点 澤井大和(東京大学医学部医学科M3) ○【討論】宅間守精神鑑定書を振り返る 植田太郎 (社会福祉法人巣立ち会) ○医療観察法による医療の実際 永田貴子(東京大学大学院医学系研究科公共健康医学専攻、国立精神・神経医療研究センター) ○累犯障害者を福祉・医療に繋げるチャンスを探る 石浦朋子(東京大学医学部附属病院精神神経科 精神保健福祉士) ○刑事施設出所後の居住・生活支援とメンタルヘルス 的場由木(NPO法人自立支援センターふるさとの会、首都大学東京大学院人間健康科学研究科看護科学域) |
| 6月19日(金) 19時~ |
3rd meeeting 「生物学的研究—Translatability を求めて」 司会 田宗秀隆先生 菅谷佑樹先生(神経生理学;狩野研) 柳下祥先生(構造生理学;河西研) |
| 7月22日(水) 19時~ |
4th meeting 「シナプス研究:精神疾患研究との接点」 司会 水谷俊介先生 岡部繁男先生(東京?学?学院医学系研究科神経細胞?物学分野 教授) |
| 9月18日(金) 19時〜 |
5th meeting 「計算論と精神科」 司会 森田進先生 1. 合原 一幸先生(東大生産技術研究所)ご講演 「カオスと脳科学(仮)」 2. 岸野 文昭さん(東大病院初期研修医2年次) 「統合失調症と計算論~古典学説からのアプローチ(仮)」 3. 浮田 純平さん(東大医学部5年生) 「統合失調症と計算論~computational psychiatryからのアプローチ(仮)」 |
| 10月21日(水) 17時30分〜 |
6th meeting 「触法少年の精神療法」 青島多津子先生(リラ溝口病院) ご講演 |
| 11月13日(金) 18時〜 |
7th meeting 「身体疾患患者の心理支援」 花村温子先生(埼玉メディカルセンター) ご講演 |
| 12月9日(水) 18時〜 |
8th meeting 司会 熊倉陽介先生 特別講演「緩和ケア領域のコンサルテーションリエゾン」 小川朝生先生(国立がん研究センター東病院精神腫瘍科) |
| 1月8日(金) 19時〜 |
9th meeting 司会 田宗秀隆先生 特別講演「精神科 × ジェネラリスト × 医学教育」 須藤博先生(大船中央病院 副院長・内科部長) |
| 2月12日(金) 19時〜 |
10th meeting 司会 水谷俊介先生 特別講演「DSM登場の前後で臨床はどう変化したか」 神尾聡先生(JR東京総合病院メンタルヘルス・精神科部長) |
実際の活動(2014年度)
| 5月16日(金)18時~ | 1st meeting 初回打ち合わせ 教育講演 「私たちのしていることは患者さんのためになっているか?」(金原明子先生 東京大学医学部精神神経科) |
|---|---|
| 6月20日(金)18時~ | 2nd meeting 特別講演「臨床疫学研究入門」 (康永秀生先生 東京大学大学院医学系研究科公共健康医学専攻 臨床疫学・経済学 教授) |
| 7月18日(金)18時~ | 3rd meeeting 特別講演 「日常臨床の疑問から研究へ」(安藤俊太郎先生 東京大学医学部精神神経科) J-club 初期研修医 木内さん |
| 7月26日 (土) | BESETO(MHRC参加奨励) |
| 8月 | 精神科サマーセミナー(MHRC参加奨励) |
| 9月19日(金)18時~ | 4th meeting 特別講演「こころの読み方、声の聴き方。 ~このピア・カウンセラーはどうやってこころと向き合っているのか~」(黒川常治さん グラフィックデザイナー・メンヘラガイド・啓発活動家) |
| 10月17日(金)18時~ | 5th meeting 「薬物療法に関する研究デザインの検討」(市橋先生 東京大学精神神経科) 「研究紹介」(柳下祥先生 東京大学大学院医学系研究科疾患生命工学センター 構造生理学部門 助教) |
| 11月28日(金)18時~ | 6th meeting 精神神経科 より 教育的講演「統合失調症の早期支援の研究について」(多田真理子先生 東京大学精神神経科 J club宇野さん |
| 12月19日(金)18時~ | 7th meeting 特別講演「子育て支援とメンタルヘルス」(門脇裕美子氏 宮城県東松島市 保健福祉部 子育て支援課 技術主任兼保健師) |
| 1月16日(金)18時~ | 8th meeting 「精神科専門研修医と語って考える、今後の精神医学・精神医療」 (田宗秀隆先生 水谷俊介先生、森田進先生 東京大学精神神経科) |
| 2月20日(金)18時~ | 9th meeting 特別講演「質的研究」(能智正博先生 東京大学 大学院教育学研究科 臨床心理学コース) |
| 3月20日(金)18時~ | 10th meeting 特別講演 「認知行動療法」(榊原英輔先生 東京大学精神神経科) 「精神疾患の遺伝学的研究?」(垣内千尋先生 東京大学精神神経科) |
実際の活動(2013年度)
| 4月26日(金)18時~ | 1st meeting 打ち合わせ |
|---|---|
| 5月17日(金)18時~ | 2nd meeting J-club 宇野さん 教育講演 「緩和ケア概論」(荒木) 「グループワーク」 (市橋香代先生) |
| 6月28日(金)18時~ | 3rd meeeting J-club 水谷さん 特別講演「発達障害の画像研究」(山末英典先生) |
| 7月26日(金)18時~ | 4th meeting 特別講演「青年期向けこころの病予防推進プログラムの紹介」(Light Ring 石井さん) |
| 8月23-24日 | 精神科夏期セミナー (MHRC参加奨励) |
| 9月14-15日 | 若手合宿 (MHRC参加奨励) |
| 10月25日(金)18時~ | 5th meeting 講義「Less is More」(荒木) |
| 11月29日(金)18時~ | 6th meeting 傾聴ワークショップ (Light Ring) |
| 12月20日(金)18時~ | 7th meeting 特別講演「1.これからの生活保障の話をしよう ~ドヤ街からみる社会階層と精神疾患~ 2.せん妄診療のコツ ~安心して入院できる病院作り~」(熊倉先生) Journal Club 大塩さん |
| 1月31日(金)18時~ | 8th meeting 特別講演「臨床心理学について」(岡村由美子先生) Journal Club 宇野さん |
| 2月28日(金)18時~ | 9th meeting 今年度のまとめ |
| 3月28日(金)18時~ | 10th meeting 特別講演「身体疾患患者の心理とその支援-チームアプローチにおける心理支援の実際」(鹿児島大学大学院臨床心理学研究科 臨床心理学専攻 中原睦美 教授) |
実際の活動(2012年度)
| 5月9日(水) 17時30分~19時 |
1st meeting 打ち合わせ |
|---|---|
| 6月1日(金)18時 | 2nd meeting J-club 今村さん 清野さん 光トポグラフィー 解説&実演 (西村幸香先生) |
| 6月22日(金)18時 | 3rd meeeting J-club 大塩さん 特別講演「チーム医療とPSW」(金原明子先生) 「保健センターについて」(大島紀人先生) |
| 9月6日(木) | 4th meeting 特別講演「医療コミュニケーション」(福田正人先生) |
| 8月23日~25日 | サマーセミナー(MHRC参加奨励) |
| 10月5日(金)18時 | 5th meeting 特別講演「就労支援と就学支援」管心先生 「神経生理学教室」 菅谷佑樹先生 J-club 井上さん |
| 11月24日(土) | PhDリトリート(MHRC参加奨励) |
| 12月21日(金)18時 | 6th meeting 特別講演「シナプス刈り込みに関わる遺伝子スクリーニング系を開発」 東京大学大学院医学系研究科神経生理学分野 助教 上阪直史 先生 J-club 浅井さん |
| 1月18日(金)18時 | 特別講演 東京大学大学院 医学系研究科国際保健学専攻 発達医科学分野 教授 水口 雅 先生 J club 荻本さん |
| 2月22日(金)18時 | 教育講演「統合失調症とその治療について」笠井先生 J club 佐藤さん 岸野さん 研修プログラム 再考 大塩さん |
| 3月15日(金)18時 | 教育講演「精神科医と基礎研究」神出先生 |
実際の活動(2011年度)
場所:精神神経科医局
| 5月28日 16:00 |
1st meeting 打ち合わせ会議 |
|---|---|
| 6月25日 15:00 |
2nd meeting Journal Club 担当者 初期 森田さん 教育的講演 「震災支援について」 荒木 |
| 7月23日 15:00 |
3rd meeting Journal Club 担当者 M4 三角さん 教育的講演 「チック障害と関連疾患―強迫性と衝動性」金生由紀子先生 |
| 9月24日 15:00 |
4th meeting NIH video session Journal Club 担当者 M1 廣瀬さん M2 井上さん |
| 10月22日 15:00 |
5th meeting NIH video session 研究紹介 神経細胞生物学 岩崎・石田先生より 教育的講演 「ワークライフバランスとこころの健康」島津明人先生(精神保健学) Lab tour 神経細胞生物学 水口先生 Journal Club 担当者 M4田宗さん |
| 11月26日 15:00 |
6th meeting NIH video session Lab tour 精神保健学 千葉さん Journal Club 担当者 M2 岸野さん M3今村さん 教育的講演 「社会精神医学~臨床・研究・政策を行来する~」 西田淳志先生(東京都精神医学総合研究所) |
| 12月10日 15:00 |
7th meeting NIH video session Lab tour 精神医学(八幡) Journal Club 担当者 M3清野さん こころの発達医学(桑原) |
| 1月14日 15:00 |
8th meeting Lab tour 分子精神医学(岩本) 疾患生命工学センター構造生理学(柳下) Journal Club 担当者 M2 大塩さん |
| 2月25日 15:00 |
9th meeting Lab tour 心療内科学 教育的講演 尾藤晴彦先生(神経生化学) 「神経可塑性と回路構築を制御するCaMK情報伝達系 -ニューロンとシナプスの階層を結ぶロジックを求めて-」 |
| 3月24日 15:00 |
10th meeting まとめ |
実際の活動(2010年度)(コース全体の活動のみを記載)
| 6月5日 | 打ち合わせ会議 1st meeting |
|---|---|
| 6月26日 15時 | 2nd meeting 教室紹介① 精神医学(笠井)構造生理学(柳下)分子精神医学(岩本) Journal Club 担当者 M1 井上さん M3 三角さん 教育的講演 八幡憲明先生(精神神経科) |
| 7月3日~4日 | 若手研究者合宿(精神医学教室主催) |
| 7月31日 15時 | 3rd meeting 教室紹介② こころの発達診療部 神経細胞生物学 Journal Club 担当者 M2 清野さん 教育的講演 鈴木友理子先生(国立精神・神経医療研究センター) |
| 8月26日~28日 | 精神科 夏季セミナー |
| 9月11日 15時 | 4th meeting 教室紹介③ 心療内科 精神保健学 神経生理学 Journal Club 担当者 M2 今村さん 初期 杉浦さん 教育的講演 伊勢田 堯先生(都立松沢病院) |
| 10月23日 15時 | 5th meeting Journal Club 担当者 M2 今村さん 初期 杉浦さん 教育的講演 小川朝生先生(国立がん研究センター) |
| 11月6日 | 大学院リトリート(精神医学分野) |
| 11月27日 15時 | 6th meeting Lab tour; 精神保健学 神経細胞生物 構造生理学 Journal Club 担当者 M1 大塩さん |
| 12月4日 15時 | 7th meeting Journal Club 担当者 M3 常盤さん Lab tour; 心療内科 教育的講演 島津明人先生(東京大学大学院医学系研究科精神保健学分野) |
| 1月15日 15時 | 8th meeting Lab tour;分子精神医学 神経生理学 精神医学 Journal Club 担当者 初期 村山さん |